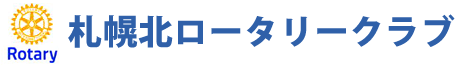第2366回例会
第2366回例会(2025年5月26日)

「青少年の未来に繋がる関わり」
青少年奉仕委員長 蓑輪 隆宏 会員
青少年を広辞苑で引くと「青年と少年。こどもとおとなとの中間の若い人たち」と書いてあります。
正直、とても曖昧な基準でどう判断すれば良いのか分かりませんが、とにかく若い人なのだろうと想像します。また、マイロータリーには青少年奉仕についてこう記載されております。「インターアクト、青少年指導者育成プログラム(RYLA)、ロータリー青少年交換などを通して、青少年や若い世代の社会人がリーダーシップ能力を伸ばせるよう支援することです」と。
では、ロータリーで言うリーダーシップ能力とはどんな能力なのでしょう。調べてみますと、高潔性、専門知識、奉仕への熱意というロータリアンの資質を体現する模範となることですとありました。皆さんいかがでしょう。解釈は無限にありますので、ここでは意見は控えます。
私が関わる青少年とはどんな方々かを説明致します。まずは自分の職場で共に働く若い方々、そして、卒業同学部の後輩と学生、加えて、母校で部活動を共に頑張る学生たちが主でございます。つまり、日々の専門的な仕事を通して多くの患者さんと関わる青少年、専門職に就くため日々、深い学びと厳しいと実習に励む青少年、勉強だけではなく部活動に夢を膨らませ心身を鍛える青少年であります。
彼等彼女らはおかれている立場、現在地は一人ひとり異なりますが、この時代、将来に何かしらの恐れと不安を抱えているのは一緒だと感じます。
今回、そんな青少年の皆さんと、自分が普段どう向き合って関わっているのかということを浅い知見と経験からですが簡単にまとめてみましたのでお話し致します。
若い人たちと関わる時に大切にしていることは、彼らと一緒に未来に視点を向けることです。何故なら、未来は若い人たちのものであり、どうにでもコントロールが出来、変えられるものだからです。コントロール出来ることにフォーカスが当たると人は若者に限らず、「やれば出来るかも」と前向きな気持ちになります。因みに、過去と他人は変えられませんしコントロール出来ませんので、そこにフォーカスが当たりだすと閉塞感が漂ってきます。そのようなことで、若者と向き合う時は未来思考のスタンスのもと「人生の目的と人間関係」について一緒に考えるようにしております。
まず、最初にすることは、一人ひとりの心の現在地を確認することです。その際、下記の2.6.2の法則を使用します。今の自分の心がどうなのか直感で当てはめてもらいます。
2 イキイキ族 (人財)
6 モヤモヤ族 (人材)
モンモン族 (人在)
イヤイヤ族 (人災)
2 バイバイ族 (人罪)
これは、人が集まり集団になると上記のような現象に分かれることが多いという理論です。自分の心は自分でしか理解出来ませんので、今、自分がどの族に位置しているのか確認して貰うことから始まります。
では、上位2割のイキイキ族と下位2割のバイバイ族の違いはどこにあるのでしょう。違いは二つあると考えます。
まず一つは、人生の目的が明確であるかどうかです。自分は誰のため、何のために生きているのか、何故頑張るのか。そしてそのために今、何をしているのかを明確に理解しているかです。目的(ゴール)が明確にある人はそこに向かって動き出したその瞬間からイキイキしてきます。
二つ目は、自分の基本的欲求のバランスを知っていて、それが今、どんな状況なのかを理解しているかです。この二つをしっかり理解出来ている人たちは上位に位置しますが、そうでない人たちは残念ながら下位に落ちていってしまう傾向にあります。
現在地が分からなければ、ゴール(目的)へ向かってのナビの設定が出来ません。よってゴールを目指したいのなら、まず自分が置かれている現在地を知ることが重要です。
ただ、大変なことは自分の基本的欲求を満たす真の目的を自分の心の奥底から引っ張り出すことです。この部分はとても深い話ですので、ここでは割愛させて頂きますが、人はゴール(目的、理念、ビジョン、ドメイン)の在り方が決まればあとはやり方を間違えなければ道を逸れることは少なくなります。あとは諦めずやるだけですが、そこから先は、目標の設定、計画化、日々の実践のサイクルを回すフェーズに入りますが、このサイクルはあくまでも自分に合った目的が土台にあってのものです。
次に、重要なことはこのサイクルを適切に回すための人間関係の充実です。人間社会で生きていく以上、この人間関係はとても重要なものですし、成功の85%は人間関係で決まるという言葉もございます。仕事でもプライベートでもパワーパートナーを増やして、成果を上げ気分良く生きることは幸せなことだと思います。その基本は目的に則った人間関係の構築ですが、プライベートはただただ楽しさ優先で良いかもしれません。一方、仕事となると、そうはいかなく、楽しさだけでは成果は上がりません。「信頼」という正しさも加わった人間関係が必要となってくることでしょう。
あと、人間関係向上の目的はもう一つございます。
それは、良い(いい)ご縁に巡りあうことです。ご縁はお金では買えないものでかけがえのないものです。そこで人間関係向上の身に付けたい七つの習慣を示します。
1.批判する→傾聴する
2.責める→支援する
3.罰する→励ます
4.脅す→尊敬する
5.文句を言う→信頼する
6.ガミガミ言う→受容する
7.褒美で釣る→意見の違いを交渉する
長年の習慣を変えることはそう簡単ではないかもしれませんが、人間関係の改善を図りたい方は是非、実践してみてはいかがでしょう。人間関係が良くなれば目的も自ずと肯定的なものに変わる可能性があります。そう考えると、目的と人間関係は一対のものと考えて良いかもしれません。
また、持って生まれた個人の「性格」は中々変えられませんが「思考」は変えられますので、若い人たちには是非、肯定的な思考のもと自分の無限の可能性を信じて頑張る選択の人生を歩んでくれたらと思います。
今の世の中は「やり方」中心になっているように感じます。そんなときだからこそ若者と「在り方」を一緒に考え、語り合える環境がもっと増えたらと思います。そして、私はまだまだ未熟ですが、自らゴールに向かって歩む、青少年の足元を少しでも輝らせる人になりたいとも思っております。
若い人たちには是非、「力」ではなく「愛」を土台にした人生を歩み、周りを少しでも平和にしてくれることを切に希望しております。
最後に、北海道医療大学ローターアクトクラブに属する若者が、今後この北クラブの素晴らしいロータリアンと接し、在り方を沢山学び、逞しく優しくそして心豊かな人生を歩んでくれることをお祈りし青少年奉仕委員会担当の卓話と致します。ご清聴ありがとうございました。